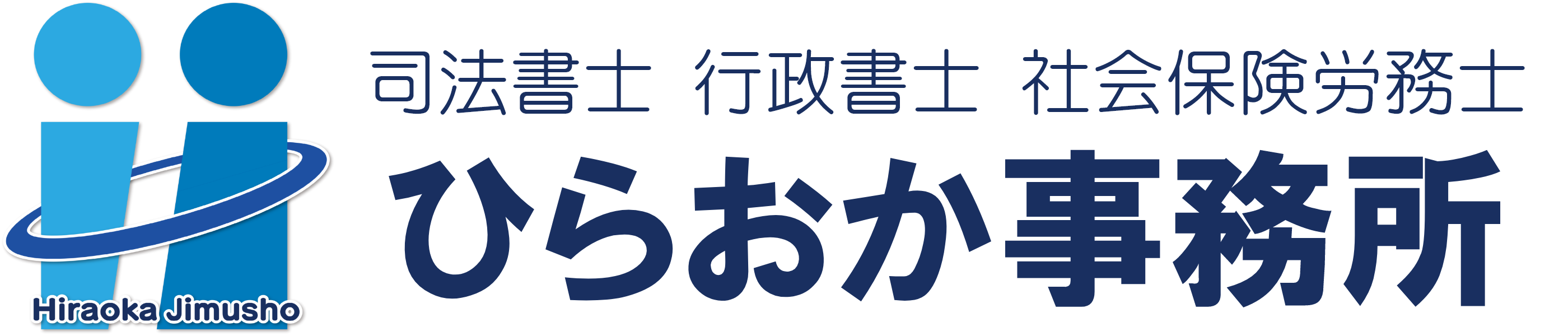遺言はしておいた方がいいのか
結論:あなたのお気持ち次第です
真っ先に結論がきてしまいましたが、それでは参考にならないので、当職が考える「あなたのお気持ち」を決める際のポイントを紹介したいと思います。
なぜ遺言という制度があるの?
この記事を読まれている皆様にお尋ねします。あなたの財産について、今、国から、「その財産はただちに長男に分け与えるように」と指示された場合、どう思いますか?「なんで自分の財産について国から口出しされないといけないんだ!」と反発するはずです。それは、死後の財産についても同じではないですか?「自分が残した財産は自分の意思で決める」というのが大原則です。ですから、遺言という制度があるのです。法定相続は、遺言がなかったときなど、相続がうまくいかないときの時のための法的なセーフティネットです。遺言があれば、法定相続が登場する余地はないのです。
遺言をしておかないとどうなるの?
上述のとおり、法定相続が発生します。別の記事で紹介していますが、法定相続が発生した場合、全ての相続人が集まって遺産分割協議を行い、あたかも亡くなった方の分身になって、亡くなった方の財産をどのように配分するのかを決めることになります。ただし、遺産分割協議が波風立つことなくまとまるかは、誰にも分かりません。「ウチの家族は大丈夫」と思われるなら、それもひとつの選択です。その選択を否定することはありません。
どういう場合に遺言しておくといいの?
端的に言えば、法定相続だと困るときは遺言をしておくといい、という回答になります。
- 特定の人(例えば妻や障碍のある子、事業を継いだ子など)に遺産を集中させたいとき
- 直系卑属(子や孫)がいないとき
- 相続人以外の人に遺産を与えたいとき
特定の人に遺産を集中させたいときは、特定の人に遺産を相続させたくないときと裏表の関係になるかもしれません。いずれにせよ、特定の人に法定相続分を超えて相続させたいのであれば、遺言するしかありません。
子や孫がいないとき、これは、当職が強く「遺言をしておきましょう」とアドバイスするパターンです。子や孫がない状況で、自分の配偶者が亡くなったときのことを想像してみてください。配偶者が残してくれた財産について、義理の父母や義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要があります。夫婦で何十年もかけて築いてきた財産を、義理の父母や義理の兄弟姉妹につまびらかにし、自分が相続するための同意までもらう必要があります。これは精神的なハードルがかなり高いのではないでしょうか。
相続人以外の人に遺産を与えたいときは、遺言以外にうまく行く方法がありません。実務でよくあるのが、高齢の単身者の面倒を、義理のきょうだいや甥姪がみているというパターンです。自分の老後を一生懸命に世話してくれた人に少しでも恩返ししたいと思うのが人の情だと思いますが、義理のきょうだいは相続人になることはありませんし、甥姪は相続人になる可能性がほぼありません。このような人に遺産を譲り渡したいのであれば、遺言をするしかありません。法定相続人がいないのであれば、特別縁故者への財産分与という手続がありますが、これには家庭裁判所の審判が必要なため、きちんと財産を譲り渡せるか未知数です。
当職の思い
最初に述べていますが、死後の財産の処分は「自己の意思」に従って行われるのが最善だと思います。たとえ「法定相続分どおり相続するように」という遺言であったとしても、それは自分で判断して決断した結論であり、「法定相続になってしまった」とは全く意味合いが異なります。すべての人が遺言をしておくのが理想ではないでしょうか。